開成高校 2025年入試 数学解答速報・教科別分析
教科別入試問題分析
2025/2/10(月)に実施された開成高校の入試について、数学の解答速報を掲載しています。
開成高校 2025年 教科別入試問題分析
英語
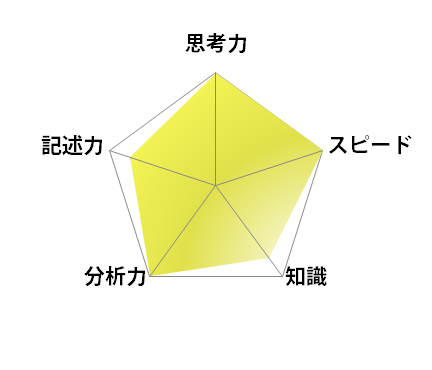
1 物語文の読解(約800語):小問数11
辺境に暮らす2人の羊飼いについての物語文です。文学的な表現が多く含まれ、受験生は内容把握に相当苦労したと思われます。英文和訳の問1、および下線部が表す内容を選択して答える問4は、地形などの状況を類推する必要がある難問でした。
2 説明文の読解(約600語):小問数11
「創造性」と「創造的思考」についての説明文です。並べかえ英作文の問1は、中間部分が指定されたあまり見慣れない形式で、かなりの思考力が求められました。問5の英文和訳は、文中の単語こそシンプルではありますが、自然な日本語に意訳する力が必要な問題でした。
3 同音異義語:小問数4
各組の英文それぞれの空所に入る、発音が同じでつづりが異なる語のうち、指定された片方を答える形式です。英文の内容や設定に工夫が見られ、即座に解答を導くのが難しかったと思われる問題も複数含まれています。
4 正誤:小問数2
6つの英文の中から、文法的・語法的に誤りを含まないものを2つ選ぶ形式です。開成高の正誤問題としては標準的な難度だったと言えます。
5 適語補充:小問数4
英文の空所に入る単語を、前後の内容から推測して答える形式です。(1)「徒歩圏内」を表す熟語など、自然な英語表現の知識が問われました。
6 並べかえ英作文:小問数3
与えられた日本語の意味になるように、単語を並べかえて英文を完成させる問題です。高校レベルの語彙や文法知識を要する問題でした。
7 リスニング:小問数12
Part A~Cの3つに分かれています。図表を参考にして図書館の利用時間を計算するなど、放送内容の聞き取り+αの作業が必要となる形式は、開成高リスニング問題の特徴の1つと言えます。
| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||
| 2025年 | 物語文 | 説明文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2024年 | 物語文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2023年 | エッセイ | 説明文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2022年 | 物語文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2021年 | 物語文 | 説明文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
数学
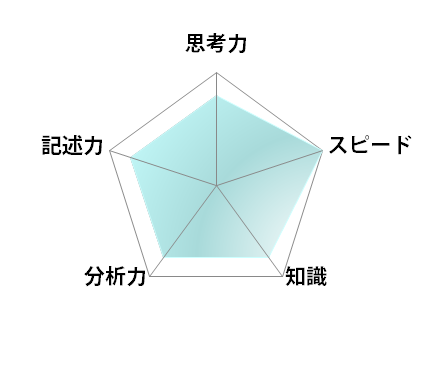
1 ピタゴラス数
ピタゴラス数に関して考察していく問題でした。整数の性質の理解が問われていましたが、開成高の受験生であれば小問どうしのつながりを意識して解くことができたと思われます。(4)についても、類題演習の経験があったと思われるので、落ち着いて正解を目指したいところでした。
2 正方形と正三角形の組合せ
正方形の中に正三角形が入った合同な4つの図形を、対称に配置した図に関して考える問題でした。(3)が穴埋め形式であることも含め、大問全体を通して、誘導が設定されていました。一つ一つの設問は決して難しくはないので、完答を目指したい問題でした。
3 ヒストグラムと箱ひげ図
2種類のテスト結果に関して、与えられたヒストグラムと箱ひげ図から、データの状況について考察する問題でした。文章量や図の見た目で難しく感じた受験生もいたと思われます。しかし、問われている内容は標準的で、特殊な解法が要求されているわけではありません。時間をかけてでも慎重に状況を整理し、考えていきたいところでした。
4 放物線と直線の交点
直線と放物線の交点について考える問題でした。直線の式の切片の値が複雑であったため、解法は分かっていても計算が思うように進まなかった受験生も多かったことでしょう。最後の小問まで、高い計算力と丁寧な処理が求められました。
| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |
| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2021年 | ● | ● | ● | ● |
国語
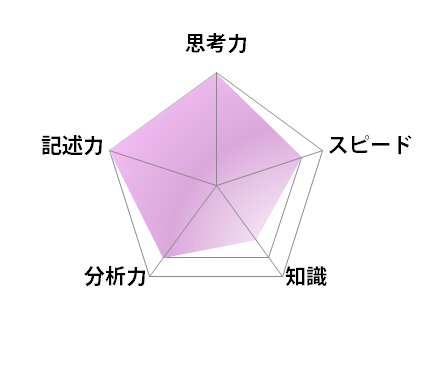
1 谷原つかさ『「ネット世論」の社会学』
「世論」という言葉のあいまいさを指摘しつつ、いわゆる「ネット世論」について考察を加えた論説文です。文章は複数の節で構成されていて、それぞれの範囲から記述が4問出されました。2021年以降、記述の一部に字数制限が設けられていましたが、2025年入試においては大問1~3までのすべての記述で字数制限がなくなりました。解答欄の長さは設問ごとに異なっているため、従来どおり何をどこまで書くかをよく考えて解答する必要があります。漢字は全4問で、いずれも標準的な難度でした。
2 ハルノ宵子『隆明だもの』
思想家・詩人の吉本隆明を父に持つ筆者が、父の臨終に際して思ったことを回想した随筆文です。文章は約1ページ分の長さしかなく、文学的文章の大問としては異例の短さでした。設問は字数制限のない記述2問のみで、解答欄はそれぞれ2行分用意されています。設問数が少ない開成高では1問1問の配点も大きいため、着眼点がずれてしまうと大量失点を喫する可能性があります。設問の意図を正しく掴み、要点を外さずに解答を作成することがポイントだったと言えるでしょう。
3 『源氏物語玉の小櫛』
江戸時代の国学者・本居宣長による文章の一節が出題されました。やや長めでストーリー性のない文章ではあるものの、具体例は豊富で論旨も明確です。設問の大半を記述が占めていますが、いずれの解答欄も0.5~1行程度と短く、端的に解答をまとめる必要がありました。そのほか記号選択2問では、作者の主張を正しく理解することが求められています。
| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |
| 2025年 | 谷原つかさ『「ネット世論」の社会学』 | ハルノ宵子『隆明だもの』 | 『源氏物語玉の小櫛』 | - |
| 2024年 | 國分功一郎『目的への抵抗』 | 岩城けい『M』 | 『遠思楼詩鈔』 | - |
| 2023年 | 宮野真生子の文章 | 正宗白鳥『吉日』 | 『今昔物語集』 | - |
| 2022年 | くどうれいん『氷柱の声』 | 内田樹『武道論』 | 『新花摘』 | - |
| 2021年 | 鈴木大拙の文章/ウスビ・サコの文章 | 『御伽草子』 | - | - |
理科
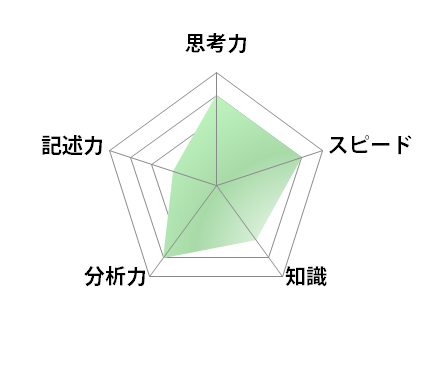
1 運動(物理)
題材となっている実験は入試でよく見られる一般的なものでした。一方、条件設定や単位などは、受験生にとって見慣れないものが多くなっていました。実験内容についてよく理解していることを前提として、問題の条件を一つずつ確実に読み取る力が求められました。近年、開成高の物理分野では、問題を読み取る力を要求される傾向が見られます。
2 化学変化(化学)
一部を除き、基本的な知識と計算方法を理解していれば正解できる内容でした。開成高の過去の入試問題でくり返し出されている内容も含まれていたため、高得点をねらえる大問だと言えます。
3 生態系、動物(生物)
生態系に関する基礎知識を確認する問題と、受験生が初めて見るような実験に関する問題でした。実験の状況を把握するのに時間がかかること、与えられた情報が最小限に絞られていることから、設問数に対して時間がかかる大問だと言えます。実験の条件や結果を細かい部分までくり返し確認することが求められ、慎重さと粘り強さが求められました。
4 天気、地質、天体(地学)
宇宙飛行士の言葉をテーマとして、地学分野の各単元からの小問集合形式の問題でした。開成高の地学分野では、過去にも同様の形式が見られました。基本事項を高いレベルで理解していることに加えて、図や表の情報を丁寧に読み取る力が求められました。
| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |
| 2025年 | 運動 | 化学変化 | 生態系、動物 | 天気、地質、天体 |
| 2024年 | 電流 | 中和 | 細胞、生殖、遺伝 | 天体 |
| 2023年 | 水圧 | 化学変化 | 人体 | 岩石、火山、天気、天体 |
| 2022年 | 電流、磁界 | イオン、中和 | 遺伝 | 火山、岩石 |
| 2021年 | 仕事、運動とエネルギー | 化学変化 | 植物、動物、細胞 | 天気、地質 |
社会
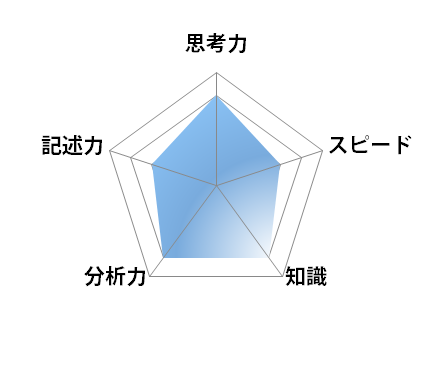
1 地理総合
山陰地域に関連して幅広い分野から出題されました。日本地理・世界地理に加え、歴史分野の内容も含まれており、分野を横断する総合的な知識とそれを運用する力が試されました。地形図に関する出題が例年より多く、いずれも慎重に読み取らなければ正解を導けないものでした。これに加え、複雑な資料をその場で分析しなければならないものや、思考力を求められる文章記述問題など、出題形式が多岐にわたり、全体的にボリュームのある構成であったため、時間配分にも注意が必要でした。
2 歴史総合
歴史の中の人・物の移動をテーマとした総合問題でした。年代順の配列や正誤の判定、語句記述などの形式が主でした。世紀順に記された3つの文章から問題が構成されており、それぞれの世紀における日本史の流れを正確に把握している必要がありました。求められている知識は標準的なものであり、開成高の入試問題では出題例が多い時代が扱われたこともあって、多くの受験生が取り組みやすいと感じるような大問でした。
3 公民総合
情報化社会におけるリスクを題材とした公民の総合問題でした。開成高で出題頻度が高い国際政治や人権に加えて、選挙、消費生活、企業など幅広い単元から出題されました。突出して難度の高いものはありませんでしたが、定着が不安定になりがちな公民分野において、各単元まんべんなく知識が身についているかどうかが試されるような問題構成でした。正誤判断の問題では、一部に複数の正答を選ばなければならない形式のものもありましたが、難度は標準的であったため、選択肢を丁寧に吟味すれば十分に対応できるものでした。
| 年 | 日本地理 | 世界地理 | 日本史 | 世界史 | 政治 | 経済 |
| 2025年 | 地形図・気候・産業 | 気候・都市 | 古代~現代 | 古代~現代 | 国際政治・選挙・人権 | 消費・企業・金融政策 |
| 2024年 | - | 地形・統計資料 | 古代~現代 | 古代~現代 | 憲法・国会・地方自治 | 企業・財政 |
| 2023年 | 地形・気候・産業 | 地形 | 古代~近代 | 近現代 | 人権・選挙 | 価格・労働・環境問題 |
| 2022年 | 地形・災害・地形図 | 地形・気候・地図 | 古代~現代 | 古代・中世 | 国会・内閣・人権 | 環境問題 |
| 2021年 | 人口・交通 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 古代~現代 | 国際政治・地方自治 | 財政 |
難関高校合格を目指す方へのおすすめコンテンツ
SAPIX中学部の公開模試の過去問題(数学)から、開成高、国立大附高、早慶高、難関私立・都県立トップ校など難関高校合格を目指す方にお勧めの問題をピックアップしました。ぜひ、挑戦してみてください。
【開成高攻略】数学の模試作問者が「視点・考え方」を語ります(問題付き)
SAPIX公開模試の過去問題(数学)から、開成高の入試本番を想定したとっておきの一題を厳選。作問者自らが、「なぜこの問題を出したのか」「難度をどう調整したのか」「受験生がどのように解くことを想定したのか」といった視点・考え方を紹介します。
動画とインタビューで魅力をお伝え!開成高校特集

【動画】SAPIX卒業生対談「開成・筑駒高から東大へ」

