灘高校 2025年 教科別入試問題分析
教科別入試問題分析
英語
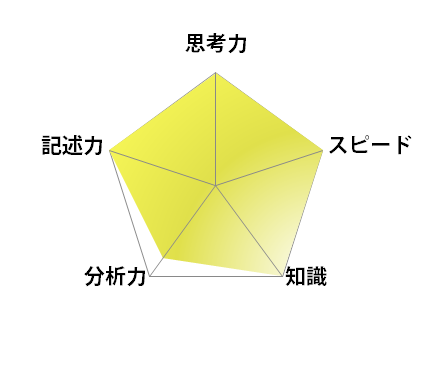
1 エッセイの読解(約660語):小問数11
日本に滞在経験のある外国人の視点から見た「変わらない」日本社会をテーマにしたエッセイです。高校入試レベルを越えた単語、熟語が語注なしで出されています。
2 リスニング問題:小問数5
紙飛行機コンテストの思い出に関する放送を聞き、記号で答える問題です。試験開始約15分後に始まります。
3 適語句選択:小問数3
英文の空所に入る単語、熟語を記号で答える問題です。高度な語彙と文脈判断が求められました。
4 語彙定義:小問数3
英語で書かれた単語の定義を参考にし、短い英文の空所に入る語を適切な形にして答える問題です。
5 説明文の読解(約610語):小問数9
国や地域間における、時間感覚に基づいた文化の違いに関する説明文です。問4の英文和訳では文法知識を正確に反映できるかどうかがポイントでした。
6 正誤:小問数3
4年連続で正誤問題が出されました。標準的な難度です。
7 エッセイの読解(約550語):小問数15
聖歌隊の素晴らしさについてのエッセイです。英文和訳の問4、6では抽象的な英文を日本語で換言する力が問われています。全体的に日本語の表現力が問われた年と言えます。
8 和文英訳:小問数3
日本語を英語に直す問題です。英語で表すのに工夫が必要な設問も含まれていました。
9 自由英作文:小問数1
ある英語の詩の一節を読み、自分の意見を英語で記述する問題です。2023年にも詩に関する出題があり、抽象度の高い表現を分かりやすく換言する力がここでも求められています。
| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||
| 2025年 | エッセイ | 説明文 | エッセイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2024年 | エッセイ | エッセイ | エッセイ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2023年 | 物語文 | エッセイ | 物語文 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2022年 | エッセイ | エッセイ | エッセイ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2021年 | ノンフィクション | 説明文 | エッセイ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数学
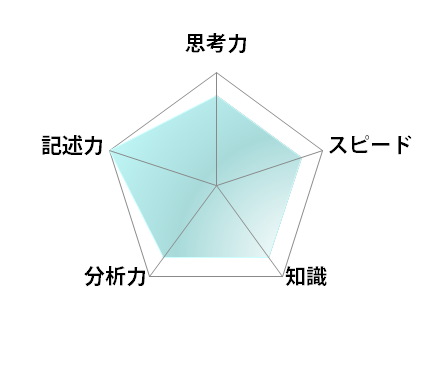
1 小問集合
(1)因数分解、(2)二次方程式、(3)確率、(4)折り返し図形の4問でした。いずれも取り組みやすい問題ですので、ここでの失点はできる限り避けておきたいところです。
2 証明問題
1つの頂点を共有した2つの正方形についての証明問題でした。有名な構図ですので類題の経験があった受験生が多かったと思われます。(1)(2)ともに短時間で記述したい問題でした。
3 二次関数
2つの放物線と直線についての問題でした。(1)は基本問題、(2)も方針は立ちやすいと思われますので、丁寧に計算をして確実に正解を積み重ねたいところです。
4 平面図形
三角形の面積や線分の長さについて求める問題でした。設定自体は典型的な問題で内容も灘高受験生にとっては基本レベルです。(1)の計算で多少手間がかかりますが、落ち着いて計算し、完答を目指したい大問でした。
5 場合の数、確率
引いたカードに書かれた金額を支払うという設定の問題でした。(1)は条件をしっかり把握できれば正解できますが、(2)は方針が立たなくて敬遠した受験生も多かったと思われます。
6 空間図形
直方体内部にできる2つの三角錐の共通部分について考察する問題でした。難度の高い問題ですが、他校で何度か出題されたことのある構図ですので、類題を経験したことがあるかどうかで差がついたと思われます。この大問に時間を残せたかどうかもポイントだったことでしょう。
| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |
| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
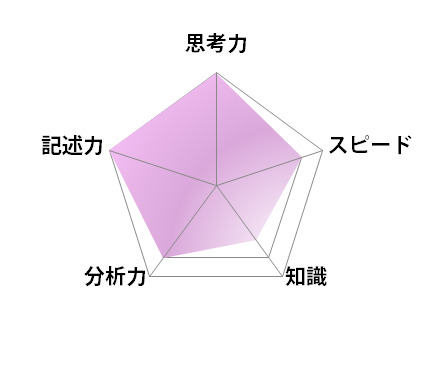
1 北村匡平『遊びと利他』
数種類のブロック玩具の特徴と、それらの遊び方に現れる利他性の違いについて述べた論説文からの出題でした。それぞれの玩具と遊び方に現れる違いを落ち着いて整理しながら読んでいけば、文章内容を理解することは難しくなかったでしょう。漢字の書き取りは2024年と変わらず9問でしたが、要求される記述の量は減少し、2023年と同程度になりました。また、灘高の国語としては珍しく、抜き出しも1問ありました。
2 高瀬隼子『犬と散歩をした話』
かつて飼っていた犬との思い出や、飼い犬に対する思いを綴った随筆文からの出題でした。全体的に平易な言葉で書かれていて、読みにくさを感じた受験生は少なかったと思われます。ただし、ところどころに注意深く内容を読み取る必要のある表現があり、それらの内容をしっかりと読み取れたかが得点を伸ばせたかどうかのポイントでした。字数制限のない記述が6問出された点は2023年・2024年と同様でしたが、記述量は2024年と比べてやや減少し、2023年並みに戻りました。しかし、一見しただけでは何を問われているのかわかりにくい問題もあり、簡単な大問ではありませんでした。
3 『続古事談』
灘高の古文では2022年から説話の出題が続いています。2025年は、平安京から福原京への遷都にまつわる場面を描いた鎌倉時代の説話集からの出題でした。文章内容の細部まで理解することは難しかったかもしれませんが、大意を把握することができた受験生は多かったのではないかと思われます。記号選択・記述ともに難度は標準的だったので、確実に得点しておきたい大問でした。
| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |
| 2025年 | 北村匡平『遊びと利他』 | 高瀬隼子『犬と散歩をした話』 | 『続古事談』 | - |
| 2024年 | 谷川嘉浩『スマホ時代の哲学』 | 梯久美子『水俣、石牟礼さんへの旅』 | 『閑居友』 | - |
| 2023年 | 若松英輔『沈黙のちから』 | アーサー・ビナードの文章 | 『宇治拾遺物語』 | - |
| 2022年 | 信岡朝子『快楽としての動物保護』 | 赤坂憲雄『旅学的な文体』 | 『和歌威徳物語』 | - |
| 2021年 | 岡田暁生の文章 | 渡辺政隆の文章 | 『日暮硯』 | - |
理科
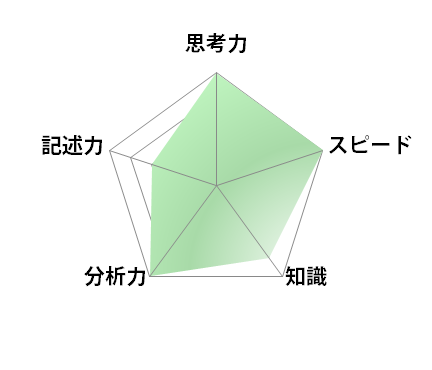
1 原子と分子(化学)
高校で履修する構造式と異性体について、中学生向けにアレンジした問題でした。灘高の過去の入試でも出題されたことがあり、発展的な学習や類題演習の経験によって差がついたものと考えられます。
2 仕事、電流(物理)
仕事やエネルギーの計算問題でした。問題ごとに適切な計算方法を考える必要がありますが、個々の内容は基礎から標準レベルで、受験生の平均点も高かったことでしょう。情報の処理能力と、計算の速さや正確性が求められています。
3 地震(地学)
地震に関するさまざまなレベルの知識問題と、地震波や津波の伝わり方の計算問題でした。知識問題は過去の入試問題とは異なり、1問ごとに正誤を考える形式でした。計算問題は条件が細かく、注意が必要です。
4 気体、化学変化(化学)
問1と問2では二酸化炭素に関するやや細かな知識が問われ、学習の精度が試されました。問3以降の計算問題は難関校でときおり出されるもので、失点をなるべく防ぎたいところです。
5 動物、植物(生物)、化学変化(化学)
呼吸商という見慣れないテーマについて分析する問題でした。問2は化学の問題ですが、これ以降の問題の多くがその答えを前提としているため、注意が必要です。全体的に、動植物と栄養素に関する幅広い知識と分析力を要し、苦戦した受験生も多かったものと考えられます。
6 力(物理)
密度と圧力に関する問題でした。灘高の過去の入試で出された水圧の問題を理解できていれば、対処できたことでしょう。計算問題は桁数が多く、注意が必要です。また、2年連続で物理分野で記述問題が出されました。
| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |
| 2025年 | 仕事、電流、力 | 原子と分子、気体、化学変化 | 動物、植物 | 地震 |
| 2024年 | 電流、エネルギー、水圧 | イオン、化学変化 | 植物 | 天体 |
| 2023年 | 運動とエネルギー、電流 | 化学電池 | 植物、生態系 | 天気 |
| 2022年 | 運動とエネルギー、水圧 | 化学変化 | 人体 | 地質 |
| 2021年 | 音、運動とエネルギー | イオン、化学変化 | 微生物 | 天体 |
