慶應義塾高校 2025年 教科別入試問題分析
教科別入試問題分析
英語
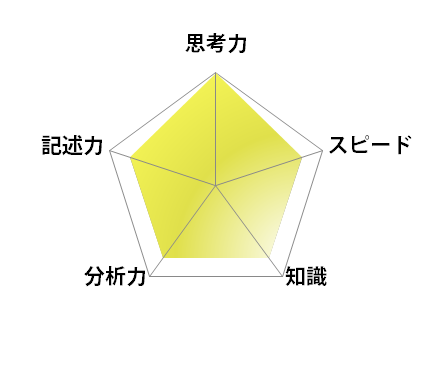
Ⅰ 空所補充選択(約250語):小問数10
慶應義塾高の生徒からの、学校を紹介する内容の手紙を読み、本文中の空所に当てはまる語句を選択する問題です。基本的な文法や語法の知識が多く問われました。8.では、相関接続詞が本文内でどのように使われているかを考えながら、選択肢内の語順を判断する力が求められました。
Ⅱ 誤文訂正(約290語):小問数10
北里柴三郎について述べた説明文です。本文中に引かれたA~Dの下線部から誤っている箇所を選んで正しい形に直す、2024年と同様の形式です。問われている知識は標準的なものが多いなか、文構造をしっかり把握して解答を考えなければならない問題もありました。
Ⅲ 説明文の読解(約400語):小問数10
世界の様々な地域で暮らす日系人について述べた説明文で、本文中の空所に当てはまる単語を答える、慶應義塾高で頻出の形式です。2023年から、補う単語の頭文字または最後の文字が与えられています。8.は直後の目的語と相性の良い動詞を考える必要がある問題で、難度が高いものでした。
Ⅳ エッセイの読解(約1500語):小問数19
同性愛者である兄を持つ筆者が、兄の苦労や周囲の人々に受け入れられるまでの過程をつづったエッセイです。徐々に変化していく登場人物の心情に着目して読み進められたかがポイントでした。本文に関連する短い文章中の語句を並べかえるBは、新しい出題形式です。文脈や選択肢の語句から文の内容を推測しつつ、正確な文法知識を用いて文を組み立てる必要がありました。Cは、同性愛者である筆者の兄に、友達の立場からかける言葉を考え、与えられた条件を含めて記述する問題です。高校入試の長文題材としては今までほとんど取り上げられなかったテーマで、難しいと感じた人も多かったと思われます。
| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||
| 2025年 | 説明文 | エッセイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 2024年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 2023年 | 説明文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 2022年 | 説明文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 2021年 | 説明文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
数学
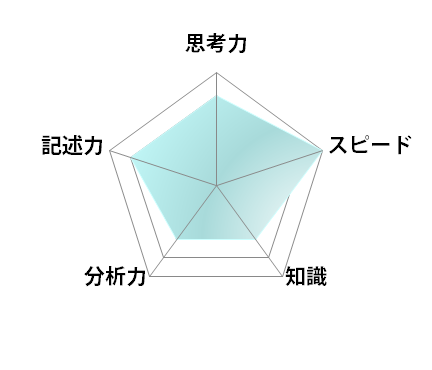
1 小問集合
(1)因数分解、(2)二次方程式、(3)連立方程式、(4)データの活用、(5)正方形に内接する円と立方体に内接する球の5問からなる小問集合でした。例年に比べると計算量も多くないため、しっかりと得点を重ねたい大問です。
2 整数
自然数を素数の積で表したときの2と3の個数について考察する問題でした。類題を解いた経験がある受験生が多かったものと思われますので、手早く処理したい大問です。
3 確率
男女3人ずつが無作為に相手を指名したときにペアができる確率を求める問題でした。(1)は基本問題ですが、(2)は答えに自信が持てなかった受験生もいたかもしれません。
4 平面図形
台形の辺と2本の対角線によって作られる三角形の面積を求める問題でした。長さの比から三角定規型の三角形を見つけられるかどうかがポイントでした。丁寧に調べていけば、完答できる大問です。
5 空間図形
正三角錐の稜線を直径とする球と正三角錐の側面との共通部分に関する問題でした。取り出すべき平面が指定されているので、難度は高くありません。図に書き入れる形式の問題がありましたが、落ち着いて取り組めば十分対応できたと思われます。
6 二次関数
放物線と直線の交点を求める問題でした。(1)(2)ともに、慶應義塾高の受験生であれば類題を解いた経験があると思われます。こちらも完答を目指したい大問でした。
| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |
| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
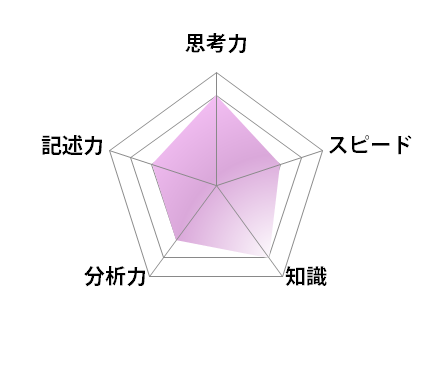
1 伊藤亜紗『手の倫理』
筆者のアメリカでの体験をもとに、道徳と倫理の違いについて論じた文章からの出題でした。受験生にとってなじみのあるテーマであり、論旨も明快で読みにくさはありません。設問は、記号選択・記述・抜き出し・空欄補充と多岐にわたります。本文の内容を理解したうえで表を読み解く設問もありましたが、文章内容を丁寧に読み取ることで解答が可能なものでした。記述は制限字数30字と15字の2問で、例年と比べ総記述量は大幅に減りました。大問2の記述に時間がかかるだけに、この大問はできるだけ時間をかけずに取り組みたいところでした。漢字の書き取り5問は標準的な難度のものが中心であり、確実に得点したいところです。
2 尼ヶ崎彬『日本のレトリック』
清少納言の詠んだ歌について考察した文章からの出題でした。古文の時代背景までしっかり学習してきた受験生にとっては、読みにくさはなかったと思われます。総小問数が15と例年に比べて大幅に減少しましたが、読解問題は記述と抜き出しのみで構成されていて、時間のかかりやすい大問でした。慶應義塾高の記述は例年字数制限のあるものが出されていましたが、2025年は字数制限のない記述が1問ありました。いずれも落ち着いて文中に手がかりを求めながら考えていくことで対応できたため、失点を避けたいところでした。抜き出しは解きやすいので、手早く片付けて記述に時間を使うことが求められました。知識分野では、難度の高い漢字の書き取り5問のほか、歴史知識や一般常識にも関わる文学史を答えさせる設問が出されました。慶應義塾高では例年さまざまなジャンルの知識が問われるので、しっかりと対策しておくことが必要です。
| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |
| 2025年 | 伊藤亜紗『手の倫理』 | 尼ヶ崎彬『日本のレトリック』 | - | - |
| 2024年 | 伊藤雄馬『ムラブリ』 | 出口智之『森?外、自分を探す』 | - | - |
| 2023年 | 司馬遼太郎『峠』 | 斎賀秀夫『敬語の使い方』 | - | - |
| 2022年 | 早川文代『食語のひととき』 | 会津八一『「南京新唱」自序』 | - | - |
| 2021年 | 池内了『科学の限界』 | 泉鏡花『鏡花随筆集』 | - | - |
