東京都立高校(共通問題)2025年 教科別入試問題分析
教科別入試問題分析
英語
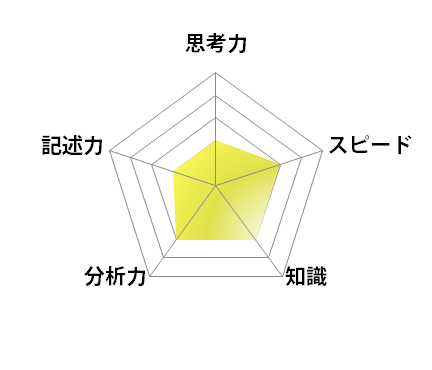
1 リスニング問題:小問数5
問題Aと問題Bの二部構成です。問題Aは設問ごとの対話文と質問を聞いて、与えられた選択肢から答えを選ぶ形式が3つあります。問題Bはある商業施設の館内放送と質問を聞いて適切な答えを選ぶ問題と、英語で答えを記述する問題が1つずつあります。
2 図表の読み取り(約840語):小問数4
大問2は1から3の三部構成です。1と2は連続した対話文で、与えられた図表をもとにして対話文中の空所を補う語句の組み合わせを選択する問題です。日本の高校生と海外からの留学生の対話文で、1では週末の予定についての対話があり、2では週末の外出先での対話があります。3は帰国した留学生からの日本の高校生へのEメールの内容に一致する選択肢を答える問題と、そのEメールへの返信の一部を3つの英文で書く問題です。大問の総語数が2024年よりも300語以上増えているため、戸惑った受検生も多かったと考えられます。
3 対話文の読解(約740語):小問数7
3人の中学生と、海外からの1人の留学生の対話文です。各自が日々の生活から興味を持ち、新しく学び始めたことについて話している対話文です。形式は例年通り、ほとんどの問題が指示語や代名詞の内容に関する記号選択で、下線部前後のセリフを中心に内容を確認することで解答できたと思われます。
4 物語文の読解(約680語):小問数7
新しいことに挑戦をするときには不安や緊張を感じることの多かった主人公が、家族や友人との会話を通じて、ボランティア活動に参加し、自信を持つことができるようになった物語文です。本文中には仮定法や原形不定詞を用いた英文がありましたが、平易で理解しやすい表現でした。問2は例年通り、本文の時系列に合わせ、英文を並べるものでした。
| 年 | 長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | |||
| 2025年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ||||
| 2024年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ||||
| 2023年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ||||
| 2022年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ||||
| 2021年 | 対話文 | 物語文 | - | - | ● | ● | ||||
数学
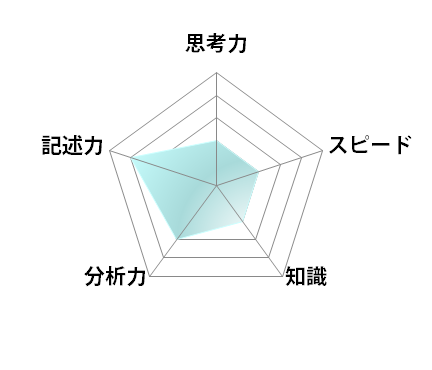
1 小問集合
〔問1〕から〔問6〕までは計算問題、〔問7〕は二次関数の変域、〔問8〕はカードの確率、〔問9〕は作図の9問からなる小問集合でした。出題内容、難度ともに例年通りのセットでした。
2 文章題
例年通り、『先生が示した問題』をもとにして生徒が問題を作ったという設定でした。数字をつけた円周上の点について考える問題で、〔問1〕は条件を理解すれば難しくありません。〔問2〕の証明問題は2点の関係を文字で表すことさえできれば立式自体はしやすかったと思われますので、最後まで記述したいところです。
3 一次関数
座標平面上の直線の式、図形の面積についての問題でした。〔問1〕〔問2〕は基本問題なので、確実に正解したいところです。〔問3〕は例年通り、座標を文字で表し、面積について立式する問題でした。対策をしてきた受検生にとっては方針は立ちやすいので丁寧に計算をして正解したいところです。
4 円
半円の円周上の点を結んでできる図形についての問題でした。〔問1〕の角度、〔問2〕①の証明問題は、例年通りの難度ですので落ち着いて対応したいところです。〔問2〕②は、複数の図形の性質を見抜く必要があるため思うように解けなかった受検生も多かったと思われます。
5 空間図形
直方体の内部にできる図形についての問題でした。例年、〔問2〕で出題されていた体積が今年は〔問1〕で出題されましたが、底面積と高さは捉えやすく、難度は高くありませんでした。〔問2〕は三角形の面積を求める問題で、高さをうまく求めることができたかどうかで差がつく問題でした。
| 年 | 計算問題 | 整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面図形 | 関数 | 二次関数 | 場合の数 | 確率 | データの活用 | 空間図形 | 球 |
| 2025年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2024年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2023年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2022年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2021年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
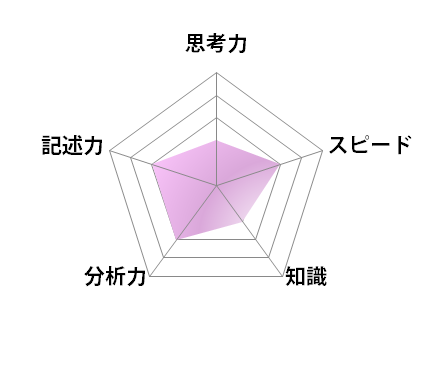
1 漢字の読み取り
漢字の読み取りが5問出されました。例年同様、標準レベルの語句が中心です。
2 漢字の書き取り
漢字の書き取りが5問出されました。一点一画を正確に書くことが求められます。
3 にしがきようこ『アオナギの巣立つ森では』
オオタカのヒナの巣立ちを見守る主人公たちの心情を描いた小説文からの出題です。小学生の主人公の視点に立って物語が進行していくため、読み取りやすい文章だったと言えるでしょう。設問は全部で5つで、すべて記号選択形式です。傍線部周辺を丁寧に読み取ったうえで、各登場人物の心情を適切に把握する力が求められました。
4 中田星矢『文化のバトンを受け継ぐコミュニケーション』
高度な技術や文化の基盤となる「社会的学習」について考察した論説文からの出題です。例示された実験の結果をよく読んで、筆者の主張を正しく理解することがポイントでした。記号選択は全4問で、うち1問は文章構成の理解に関するものでした。文章全体の大きな流れを意識して読み進める必要があったと言えます。例年同様、制限字数200字以内の条件作文も出されています。
5 河合隼雄・池田利夫の対談/前田雅之の文章
和歌に関する対談と、『六百番歌合』の解説文とを、複合的に読み取るという内容の大問でした。複数の文章の共通点や相違点を整理しながら読み進めていくことが求められています。5問すべてが記号選択で、一部にまぎらわしい選択肢を含むため、ある程度広い視野を持って丁寧に取り組む必要がありました。知識分野からは頻出の口語文法の問題が出されています。
| 年 | 文章1 | 文章2 | 文章3 | 文章4 |
| 2025年 | にしがきようこの文章 | 中田星矢の文章 | 河合隼雄・池田利夫の対談/前田雅之の文章 | - |
| 2024年 | 辻村深月『この夏の星を見る』 | 長谷川眞理子『進化的人間考』 | 久保田淳・俵万智の対談/馬場あき子の文章/高橋和彦の文章 | - |
| 2023年 | 清水晴木『旅立ちの日に』 | 信原幸弘『情報とウェルビーイング』 | 円地文子・吉田精一の対談/塚原鉄雄の文章/『新編日本古典文学全集』 | - |
| 2022年 | 村山由佳『雪のなまえ』 | 大須賀節雄『思考を科学する』 | 『山家集』/白洲正子・目崎徳衛の対談/白洲正子の文章 | - |
| 2021年 | 伊吹有喜『雲を紡ぐ』 | 堀部安嗣『住まいの基本を考える』 | 蜂飼耳・駒井稔の対談/『無名抄』 | - |
理科
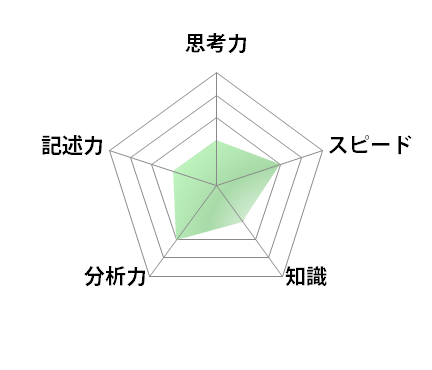
1 小問集合(物理・化学・生物・地学)
形式は例年通りで、各分野の基本的な知識や計算について確認する問題でした。一部の問いは、計算や情報の整理が必要であり、一手間かかるものでした。難度は高くないものの、慎重さや丁寧さが求められました。
2 小問集合(物理・化学・生物・地学)
レポートを読んで問いに答える例年通りの形式でした。4問中2問が完答形式であり、知識や計算の正確性が求められました。特に、そのうちの1問は問題の条件がやや複雑で、ミスしやすいつくりとなっていました。
3 地質(地学)
地層や岩石に関する基礎知識を確認する問題と、観察結果と知識を組み合わせて解く形式の問題でした。公立校の入試でよく出される問題が中心で、比較的対処しやすい大問だったと言えるでしょう。
4 細胞(生物)
タマネギを用いた細胞分裂の観察に関する問題で、大問3と同じく観察結果と知識を組み合わせて解く形式のものがありました。与えられている情報量が多く、必要な情報をすばやくかつ的確に読み取る力が求められました。
5 化学変化(化学)
教科書レベルの実験を題材として、知識や計算を確認する問題でした。知識を確認する問題の一つでは、条件の一部が伏せられており、解きにくい形式になっていました。今年は、同様の傾向が他の大問でも見られました。
6 電流(物理)
電流と磁界に関する問題で、2021年の大問6と同様の観点が多く取り上げられていました。東京都立校では、過去の入試問題と同様の観点から出題されることもあるため、丁寧な復習が重要です。
| 年 | 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 |
| 2025年 | 光、力、電流 | 物質の特徴、イオン、化学変化 | 人体、遺伝、植物、細胞 | 天体、天気、地質 |
| 2024年 | 電流、光、運動とエネルギー、力 | 化学変化、イオン、物質の特徴 | 動物、人体、生態系、植物 | 天気、地質、天体 |
| 2023年 | 光、運動、電流 | 化学変化、物質の特徴、イオン | 生態系、植物、生殖、人体 | 岩石、天体、天気 |
| 2022年 | 光、電流、力、運動とエネルギー | 化学変化、物質の特徴、イオン | 人体、植物、遺伝 | 天気、天体、地質 |
| 2021年 | 音、力、運動、電流 | イオン、物質の特徴、化学変化 | 人体、遺伝、動物、植物 | 地震、天体、天気 |
社会
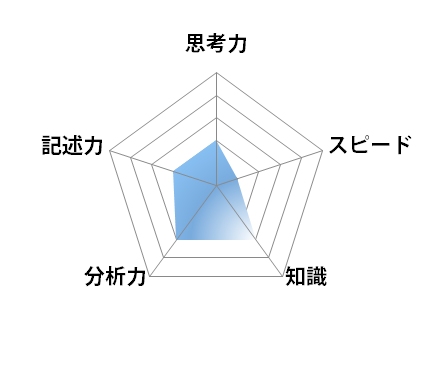
1 小問集合
地形図の読み取り、歴史用語・公民用語の選択という例年通りの出題でした。資料として与えられた条件を満たす地形図を選択する問題は、ルートマップと地形図の違いを認識しておく必要がありました。
2 世界地理
条件に当てはまる都市と雨温図の選択、国の特色の選択、資料・統計の読み取りという例年通りの出題でした。国の特色を記した文章から地図上の国を特定する問題は、文章中のキーワードに着目して解答を導く定番の形式でした。
3 日本地理
都道府県の特定、統計の読み取り、資料の読み取りによる記述問題という例年通りの出題でした。記述問題は、設問条件や解答しなければならないものはなにかを明確に把握する必要があり、東京都立校の記述問題の形式を理解している受検生に有利なものでした。
4 歴史
前近代の年代整序と場所の特定、資料の読み取りによる記述問題、近現代の年代整序が出題されました。前近代の年代整序で文化史のやや細かい知識が問われたものの、過去の東京都立校の入試問題で何度も問われたことのある知識であり、対策は可能でした。
5 公民
基本的人権、条件に当てはまる法律の選択、グラフと文章の読み取り、資料の読み取りによる記述問題が出されました。東京都立校で定番のものが多く、確実に得点したい大問でした。
6 総合
国の特定、グラフと文章の読み取りが出題されました。グラフの読み取りについては、文章の内容と慎重に見比べた上で、正答を特定できる要素を見極める必要がありました。
| 年 | 日本地理 | 世界地理 | 日本史 | 世界史 | 政治 | 経済 |
| 2025年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 近現代 | 人権 | 労働・景気 |
| 2024年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 近現代 | 人権・国会・国際政治 | 財政・国際経済 |
| 2023年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 近現代 | 人権・国際政治 | 価格・租税・株式会社 |
| 2022年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 近世~近現代 | 人権・国会 | 情報社会・経済史 |
| 2021年 | 日本地理総合 | 世界地理総合 | 古代~現代 | 近世~近現代 | 地方自治 | 労働・景気 |
